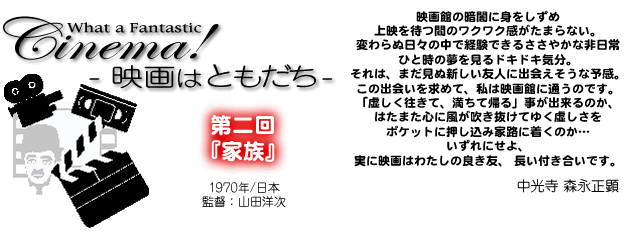 |
|||
バックナンバー
はこちら
第一回
初恋の来た道
第二回
『家族』
1971年3月、私は小学校を卒業しました。
その春休みに友人の N君に誘われるまま、
『家族』(山田洋次監督、1970年度作品)という映画を見ました。
私にとっては、映画作品と呼ぶべき映画に触れた最初でありました。
それから30年以上が経過して、
今となっては映画のあらすじと、
印象に残った シーンを断片的に、
うろ覚えで記憶しているに過ぎません。
それ故、記憶違いもあるかと思いますが…。
● 九州のとある小さな島に住む炭鉱労働者と、
その家族ー主人公である夫婦には井川比佐志と倍賞千恵子。
夫の父親、つまり、おじいちゃん役に 笠智衆、
そして2人の子供(うち1人は赤ん坊)の5人家族が、
高度経済成長の時代にありながらも、
その恩恵にあずからぬばかりか、
苦楽順逆するこの世のさだめと、
きびしい現実生活の中で新天地を求め、
北海道の開拓村をめざす長い旅物語。
● 当時、12歳であった私は、
この映画の大阪万博見物の場面にとてもひきつけられた。
何せ、ついこの間まで何度も足を運んだ会場や、
太陽の塔がスクリーンいっぱいに映し出されたのだから。
私はそのまま身じろぎもせず映画に見入った。
●見終わって、最も印象に残ったのは、家族の死であった。
この作品では二つの死が描かれている。
一つは、旅の途中、赤ん坊が熱を出し、
あっという間に亡くなるところ。
きのうまで背中に負ぶっていたわが子を、
今日はお骨にしてわが胸に抱かねばならない…
私には涙すら出なかった。
何と命とはもろく儚いものであろうか!
もう一方はようやく北海道へたどり着き、
ひとときの宴の後、主人公の父、笠智衆が
誰にも気付かれず一人静かに命終える場面である。
その死に顔は神々しく、平安そのものであった。
当時、まだ家族の死を見たことのなかった私にとって、
この二つの場面は生々しく現実味をおびて迫ってきた。
いずれ僕も家族の誰かを見送る時が来る。
大人になれば否応なく、
さまざまな困難な出来事が待ち受けているであろう人生という旅に出なくてはならないんだなあ。
漠然たる不安にかられたことを憶えています。
● それから11年後、私は自宅で往生をとげた祖父の枕元で読経した。
祖父はその身をもって
“人は死ぬのだ。 たった独りでこの地上から消えてゆくのだ”
という事をあらためて教えてくれた。
無言の説法であった。
私は合掌しながら
「祖父は人生の旅を終え、お大師さんと手をつないでいのちのふる里へ帰ってゆくんだ」と実感した。
● その祖父の死から20年が経過した現在、
私は妻子3人を伴い人生の折り返し地点を曲がった。
今でも3月になると時折り、
12歳の時に見たこの映画の一家の事を思い起こす。
そして想像してみる。
あれから30年以上、映画のラストで、
妻・倍賞千恵子に宿った新たないのちも、とうに生まれ、
そして成人して家族を持っている事だろうと。
● そんな私の娘も12歳。この春、小学校を卒業した。
いずれ彼女も旅立ち、人と生まれた悲しみを知るのであろうか。
私は願う。
どうかお大師さまに導かれし旅であらんことをと…。
合掌
憧西房正顕